Knowing Contentment, One Finds Lasting Joy — A Quiet Path to Happiness
もっとではなく、すでにあるに目を向けたとき、心は自由になります。
幸せって、足りないものを埋めること?
もっと頑張らなきゃ、もっと手に入れたい――
そんなふうに生きていると、いつも何かに追われているような気がしませんか?
でも、あるときふと思ったんです。
足りないのは満たす力じゃなくて、気づく力なのかもしれないって。
本当の幸せって、もしかしたらもう、手の中にあるのかもしれません。
気づいていないだけで。
知足常楽って、諦めじゃないの?
知足常楽(ちそくじょうらく)という言葉。
聞いたことがある方も多いと思います。
でも正直なところ、それって向上心がないってこと?と思ったこと、私はあります。
現状に満足していたら、成長できないんじゃないかって。
でも、よく考えると、満ち足りることを知るのは、とても大人な心の在り方ですよね。
欲望をなくすわけじゃない。
ただ、欲望に振り回されない。
そんな静かな芯の強さが、知足常楽にはある気がします。
止まらないもっと欲しいの連鎖
現代って、本当にたくさんのモノや選択肢にあふれていますよね。
スマホを開けば、誰かの成功や楽しそうな日常がどんどん流れてきます。
もっと稼ぎたい
もっと評価されたい
もっと自由な暮らしをしたい
そう願って頑張るのは、決して悪いことじゃありません。
でも、どこかで何かが足りないと感じてしまう。
その感覚に、私はずっと疲れていました。
【実体験】焦りと比較のなかで、見失っていたもの
私が30代になったばかりの頃、IT系の会社で働いていました。
周りにはバリバリ転職して年収アップした同期や、毎週のように旅行に出かける友人がいて。
SNSを見ては、なんとなく落ち込む日々。
一方の私はというと、上司との関係もうまくいかず、目の前の仕事に追われるばかり。
もっとスキルをつけなきゃと思って資格の勉強をしたり、副業を始めたりしました。
でも、結果的に得たのは疲れだけ。
心はどんどん空っぽになっていきました。
そんなある朝、通勤途中にふと立ち寄った喫茶店で、窓際の席に座ったときのこと。
朝日がちょうどコーヒーのカップを照らしていて、なんとも言えないあたたかい気持ちになったんです。
あれ、これだけで…けっこう幸せかも…
その瞬間、ハッとしました。
私はずっと、“足りないもの”ばかりに目を向けていたんだなって。
▶︎ 過去のしんどい記憶を手放すヒントはこちらの記事で書いています。
→【手放すことを学ぶ——人生の八苦を超える智慧】
知足常楽の本当の意味とは?
知足とは、何も望まなくなることではありません。
それは、今あるものに目を向ける力です。
そして常楽は、ドキドキする刺激じゃなくて、心の奥からじんわり湧いてくる静かなよろこび。
この2つが合わさったとき、初めて私たちは自分のペースで生きられるのかもしれません。
▶︎ 日々の中にある美しさを見つけるヒントはこちらで紹介しています。
→【無常の世を生きるということ】
古人たちの足るを知る暮らし
たとえば中国の詩人・陶淵明は、自然に囲まれた田園での暮らしを愛し、
「菊を東籬に採りて、悠然として南山を見る」と詠みました。
また日本の俳人・松尾芭蕉は、名声よりも自然との一体感を大切にしていた人です。
西洋でも、ヘンリー・D・ソローが『ウォールデン』で語ったように、
質素な暮らしのなかに、本当の豊かさを見出そうとする姿があります。
こうした先人たちの生き方には、今の私たちにも通じるヒントがあるように感じます。
今日からできる知足の小さな実践
1.小さな感謝リストを書いてみる
1日ひとつだけでOK。
ありがたいと思えたことをメモしてみましょう。
・朝ごはんが美味しかった
・天気がよかった
・友達と笑えた
たったこれだけでも、心が「すでにあるもの」に目を向けはじめます。
2.SNSから少し離れてみる
つい比べてしまうSNSの世界。
思い切って1日だけでもお休みしてみると、気持ちがスッと軽くなります。
代わりに、空の色を見たり、ゆっくりコーヒーを飲んだり、五感を大事に過ごしてみましょう。
3.今、ここに戻る習慣を持つ
忙しいときこそ、ちょっと立ち止まってみてください。
・深呼吸をしてみる
・目を閉じて音に耳を澄ませる
・目の前の風景をじっと見てみる
たった数分でも、心のざわめきが静まっていきます。
静けさの中にこそ、深い幸せがある
幸せは、ゴールとして手に入れるものじゃないのかもしれません。
むしろ、日常のなかにポツンと咲いているもの――
それに気づけるかどうか、なのだと思います。
▶︎ 喧騒のなかで心の静けさを保つヒントはこちらの記事をどうぞ。
→【心がざわつくとき、どう整える?】
最後に
本当の幸福は、すでに持っていたことに気づいたときに、そっと花開く
そんな言葉が、いまの私にはしっくりきます。
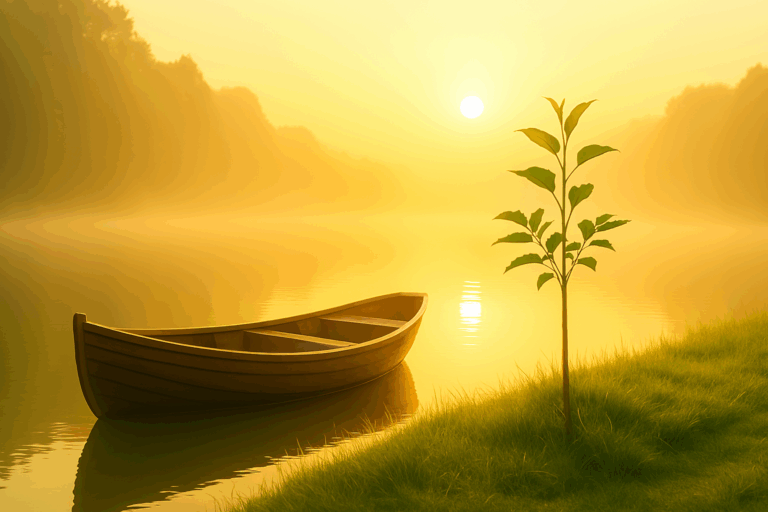
もしあなたも、足りないと感じて疲れているのなら、
ぜひ一度、立ち止まって今あるものに目を向けてみてください。
きっとそこには、思いがけない豊かさが眠っています。
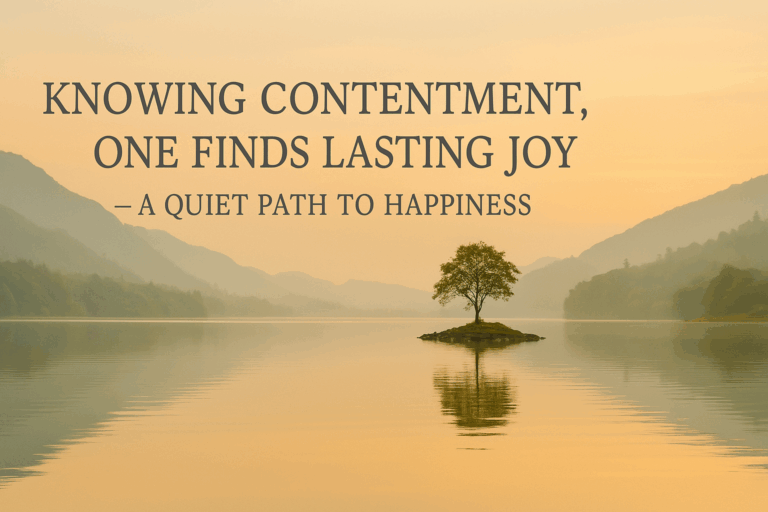
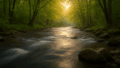


コメント