The Scope (Kakukyoku) — The Power to Decide How Far You Can Walk
最近、格局(かくきょく)という言葉を耳にすることが増えてきました。SNSやビジネスの世界だけでなく、家庭や教育現場でも、静かにその存在感を強めているように感じます。
ある人はこう言います。
「格局が結末を決める」
また、ある経営者はこんな言葉を残しました。
「人と人の差は、能力じゃない。格局にある」
なるほど。でも、格局って、実際にはどんな意味なのでしょうか?
格局とは何か?
言葉としての格局は、本来構造や配置、秩序を意味します。でも人に当てはめると、それは視野の高さ、心の広さ、もっといえば物事の見え方に関わってきます。
いまだけじゃなくて、大局を見て、感情に流されず、今だけではなくこれからを見据えられる力。
それが、私たちがここで言う格局です。
【家庭の一場面】結果よりも、その先を見る
以前、ある母親と話したときのこと。
息子さんが大学受験に失敗した直後、彼女は思わずこう叱ってしまったそうです。
「どうしてもっと頑張らなかったの?」
でも後になって、ふとこう思ったのだとか。
「私は“大学”という結果しか見ていなかった。でも、彼の人生はその一回の試験で決まるわけじゃない。彼が何を悩み、何を感じていたのかを見るべきだったんだ」
この気づきが、親子関係を修復するきっかけになったそうです。
それこそが、親としての格局が広がった瞬間だったのかもしれません。
【歴史に見る格局の差】
項羽と劉邦の話は、よく知られています。
項羽は圧倒的な力を持ちながら、その名誉やプライドに縛られて敗れました。一方の劉邦は、小さな失敗にこだわらず、大きな流れを見て人を動かし、最終的に天下を取りました。
どちらが格局のある人物だったかは、もう言うまでもないですね。
【企業の現場から】短期志向からの転換
ある中小企業の社長の話も印象に残っています。
かつては、目の前の利益を最優先にし、社員の疲弊を顧みなかったそうです。でもある日、自分の子どもが学校でいじめられていることを知ります。
原因は、SNS上で搾取する会社の社長の子どもと言われていたこと。
それがきっかけで、彼は考え方を大きく変えました。
「社員の人生や家族を大切にしたい」
そう思って経営方針を変えた結果、数年後には会社の評価も安定し、社員の定着率も上がったといいます。
短期の利益を追う視点から、長く一緒に歩む人を大切にする視点へ。格局が変われば、未来も変わるんです
――A社社長
【教育現場から】叱るのをやめて「聴く」へ
ある小学校の先生もまた、こんな経験を語ってくれました。
授業中に問題を起こしがちな子がいて、最初は言うことを聞かない子としか見えなかったそうです。
でも、ある日その子の家庭を訪問したことで状況が一変します。両親は離婚し、育児放棄に近い状態。子どもは孤独と不安の中で、助けを求めていたのです。
それを知った先生は、その日からまず話を聴くことを心がけました。
半年後、その子はクラスの中心的存在に成長。卒業式ではこう言ったそうです。
「先生は、僕を変えてくれた。怒らず、待ってくれた」
教育における格局とは、すぐに結果を求めないこと。そして、子どもを信じて待つ力なのだと、私は感じました。
格局は育てられる
格局の大きさは、生まれつきのものではありません。
後天的に、少しずつ育てていけるものです。
■ 読書で認知を広げる
歴史を読めば、盛衰が常であることを知り、
哲学を読めば、人の内面と向き合う知恵を学べる。
物語を読めば、他人の人生と自分の心がつながる感覚を持てます。
■ 視点を変える
他人の立場になってみる。
未来から今を眺めてみる。
国や文化を越えて、今の自分を問い直してみる。
この視点の変化が、格局を育てる第一歩です。
■ 捨てることを覚える
すべてを得ようとすることは、実は格局を狭めてしまいます。
「手放すことを学ぶ——人生の八苦を超える智慧」にも書きましたが、何かを手放すことで、見えてくる世界があります。
短期の勝ち負けよりも、長期の成長に目を向けていく。
それが、余裕としなやかさを生むのです。
■ 許すという力
人を裁かないこと。
自分を責めすぎないこと。
誰かを受け入れ、自分をも労わること。
それが心の余白を生み、格局を深めてくれます。
静けさの中にある、本当の強さ
格局というのは、大声で語る理想論ではありません。
むしろ、喧騒の中にいてもなお、自分の軸を静かに見つめ続ける力です。
誘惑に負けない節度。
理不尽に耐えられる沈黙の力。
成功しても驕らない謙虚さ。
それらすべてが、格局という見えない器を形づくっています。
最後に──山を抱き、星を宿すような人へ
格局とは、生まれ持った資質ではありません。
たとえ誤解されても、傷つけられても、
それでも誰かを信じる勇気を持ち続けられるか。
細い道を一歩ずつ歩きながら、心の中に育てていく“器”なのだと思います。
家庭でも、学校でも、仕事でも。
目の前の出来事だけに囚われず、その先を見ていく力が、今こそ問われています。
「複雑さをシンプルにする——大道至簡の知恵と実践」にも通じる考えですが、本質を見極めるには、見えないものに気づく目が必要です。
高みから人を見下さず、遠くまで歩んでも初心を忘れない。
山を映す瞳、星を宿す心。
それが、私たちが育てていく“格局”の証なのかもしれません。


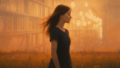


コメント