Fragility and Clarity of Humanity — Living Beyond the Grip of Bias
理性と偏見のはざまで
私たちは理性的な存在だと思い込みがちですが、本当にそうでしょうか?
実は、人間の脳は“真理”のために設計されていません。進化の歴史をひもとくと、私たちの脳は、生き延びるために発達した判断のショートカット(ヒューリスティック)の集合体なのです。
この直感的判断は、時に便利ですが、同時に私たちを偏見や誤解に陥れる罠にもなります。
認知バイアスという落とし穴
心理学のプロスペクト理論によれば、私たちは得る喜びよりも、失う痛みに敏感だそうです。投資や人間関係において、冷静さを欠いた判断をした経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
私もかつて、損失を恐れて早まった売却をしたことがあります。理性的に判断したつもりでも、後から振り返ると損失回避バイアスに飲み込まれていたのです。

この経験については、別の記事(諦めた瞬間に見えた、新しい道)でも少し触れましたが、感情に気づかずに行動すると、気づいたときにはもう遅いということもあるのです。
偏見は思考のクセから始まる
人は、無意識のうちに自分の考えを正当化し、反対意見を遠ざけがちです。これが認知的不協和です。一度偏見を抱くと、それを強化する情報ばかりを集めてしまう。まさに思考のループです。
こうした“クセ”は、やがて個人のアイデンティティの一部にまで根を張ります。さらに怖いのは、偏見が集団心理として共有されるとき。その力は、一人の理性をかき消し、分断や対立の火種になってしまいます。
三毒に支配される私たち
こうした人間の弱さを、仏教ではずっと昔から指摘してきました。『華厳経』には「貪・瞋・痴」の三毒が、すべての悪しき行動の根にあると説かれています。
•貪(とん)…もっと欲しいという終わりなき欲望
•瞋(じん)…反対するものへの怒りや攻撃心
•痴(ち)…世界を正しく見られない無知
歴史を振り返ってみても、戦争も差別も、身近な争いも、この三毒から生まれています。とても残念なことですが、人類はずっと同じことを繰り返してきたのです。
清明への一歩は気づくことから
じゃあ、私たちはどうすればいいのでしょう?
それはまず、自分の中にある感情に「気づくこと」から始まります。怒りや恐れに飲まれそうになったとき、まずは今、自分は怒っていると意識してみる。その一瞬の気づきが、心の主導権を取り戻すチャンスになるのです。
この気づきの力については、心がざわつくとき、どう整える?でも詳しく書いています。慌ただしい日常の中でも、自分の内面に静かに目を向けることが、穏やかな心を育てる第一歩です。
清明は、日常の中に宿る
清明とは、特別な悟りではありません。
それは、日々の中で何度も選び直す力です。偏見に染まりそうなとき、感情に飲み込まれそうなとき、少しだけ立ち止まって、自分の内側に光を灯す。それが「平常心」であり、「和光同塵」に通じる生き方です。
そういう意味では、清明とは“忘れる力”でもあります。過去の自分にこだわらず、柔らかく手放す。そうすることで、ようやく見えてくるものがあるのです。
このような視点は、ストア哲学と私という記事でも探っています。変えられないものを手放す生き方は、どんな時代にも必要とされる知恵です。
最後に――光はあなたの中から
人間は弱さを抱えた存在です。でもそのぶん、気づく力や変わる力も持っています。
世界を明るくする光は、いつだって“目覚めた一人の心”から始まる。
どうか、今日という一日の中に、あなた自身の清明を見つけてください。
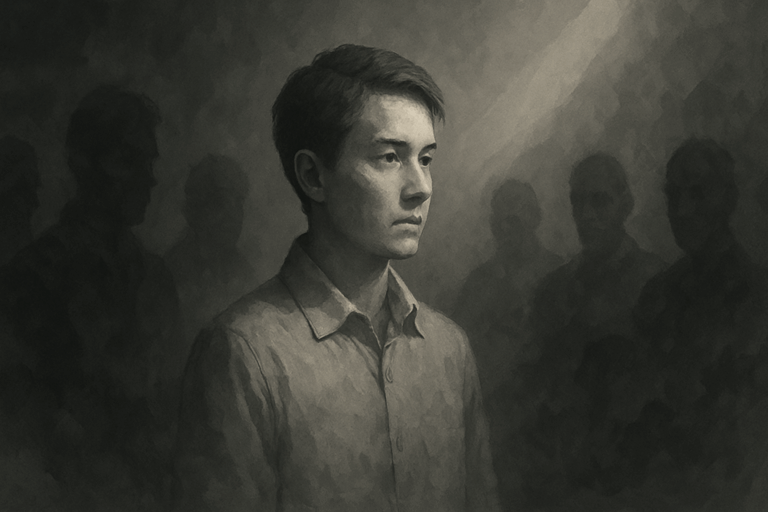
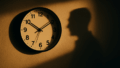


コメント