The Relationship Between Work Stress and Burnout Syndrome
はじめに:働くすべての人が直面するリスク
気づかないうちに、心の余裕がなくなっていた――そんな経験はありませんか?
現代の働く環境では、誰もが少なからず仕事のストレスを抱えています。
私も、かつてはストレスがあるのは普通と思って無理を続けた結果、心も体も動かなくなってしまったことがありました。
確かに、適度なストレスは成長につながります。でも、それが慢性的に続くと、燃え尽き症候群(バーンアウト)という深刻な心の問題に発展することもあるんです。
燃え尽き症候群って、どういう状態?
燃え尽き症候群とは、簡単にいえば心の電池が空っぽになってしまった状態。
頑張りすぎたり、自分を後回しにしすぎたりすると、知らないうちに心のエネルギーが枯渇してしまいます。
よくある症状
•感情のコントロールが効かなくなる(涙もろくなる、怒りっぽくなるなど)
•仕事に対して無関心になり、冷めた態度をとるようになる
•自分には価値がないと感じることが増える
•眠れなくなる、体調を崩す
ただの疲労とは違い、心の深い部分が傷ついている状態なんです。
なぜストレスが燃え尽きにつながるのか?
1.真面目で責任感が強い人ほど危ない
迷惑をかけたくない、失敗したくないと思う気持ちが強いと、無理をしてでも頑張ってしまいます。
私もかつては、ちゃんとやらなきゃと自分を追い詰めていました。
このあたりについては、別の記事「「完璧じゃなくてもいい」――一歩を踏み出した私が見た、新しい世界」でも、詳しく書いています。
2.周囲からの期待やプレッシャー
成果を求められる環境では、自分の価値を結果だけで判断してしまいがちです。
その結果、成果が出ない自分を否定してしまうことも。
3.相談できる相手がいない
職場やプライベートで孤立してしまうと、ストレスを吐き出す場がなくなります。
誰にも言えないという思いが、さらにストレスを深めてしまうんです。
ストレスから燃え尽きまでの流れ
燃え尽き症候群は、一夜にして突然訪れるわけではありません。
少しずつ心が擦り減っていく中で、次のような段階をたどります。
1.情熱の時期:意欲に満ちて仕事に打ち込む
2.疲れを無視して頑張り続ける:でも実は、心は疲れてきている
3.モチベーションの低下と慢性疲労
4.感情の枯渇と無力感:周囲への興味も、自分への期待もなくなる
5.完全に燃え尽きる:仕事を続けられなくなり、休職や退職へ…
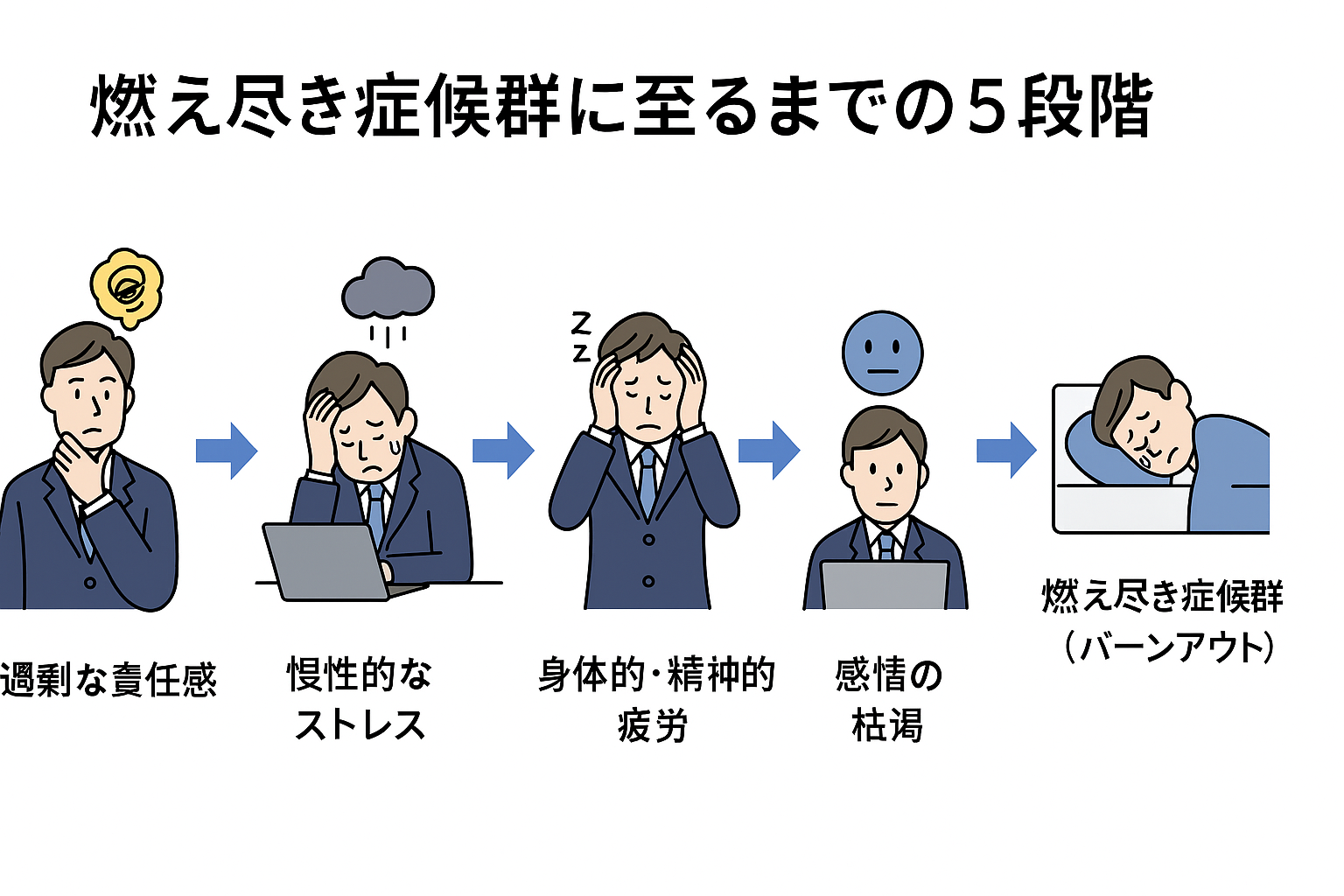
自分でできる予防とセルフケア
燃え尽きないためには、日々の小さなサインに気づくことが大切です。
1.違和感をスルーしない
•朝起きるのがつらい
•笑うことが少なくなった
•イライラしやすくなった
これらはすべて、心からのSOSかもしれません。
2.小さな自己ケアを習慣にする
•5分だけでも外を歩く
•スマホを置いて深呼吸する
•日記や今日よかったことを書く
こうした習慣は、自己理解を深め、心の軸を整える時間になります。
このあたりについては、別の記事「心がざわつくとき、どう整える?」でも、詳しく書いています。
3.働き方そのものを見直す
柔軟な働き方や相談体制を整えることも大事。
フルパワーで働き続けるよりも、休みながらでも続けられることのほうが、ずっと長く健やかに働けます。
詳しくはこちら:「働き方改革」と「心の健康」──心がすり減らない働き方を考える
燃え尽きたときの回復ステップ
すでに燃え尽きてしまったと感じたら、無理に立ち上がる必要はありません。
まずは休むこと、助けを求めることが最優先です。
1.専門家に相談する
心療内科やカウンセラーなど、第三者の視点があると、自分を客観的に見つめ直すきっかけになります。
2.自分を責めない
燃え尽きは怠けではなく、限界まで頑張った結果です。
まずは、自分に優しくしてあげてください。
3.ゆっくりと生活を整える
食べて、眠って、歩く。
この当たり前が、回復の第一歩になります。
おわりに:心の声を無視しない
まだ大丈夫と思って頑張り続けることが、必ずしも正解ではありません。
むしろ、そろそろ休もうかなと立ち止まれる人のほうが、長く前を向いて歩いていけるのかもしれません。
毎日のなかで、ほんの少しの余白を大事にしてみてください。
そして、しんどいときには誰かに頼る勇気を持ってください。
未来のあなたが、ちゃんと笑っていられるように。
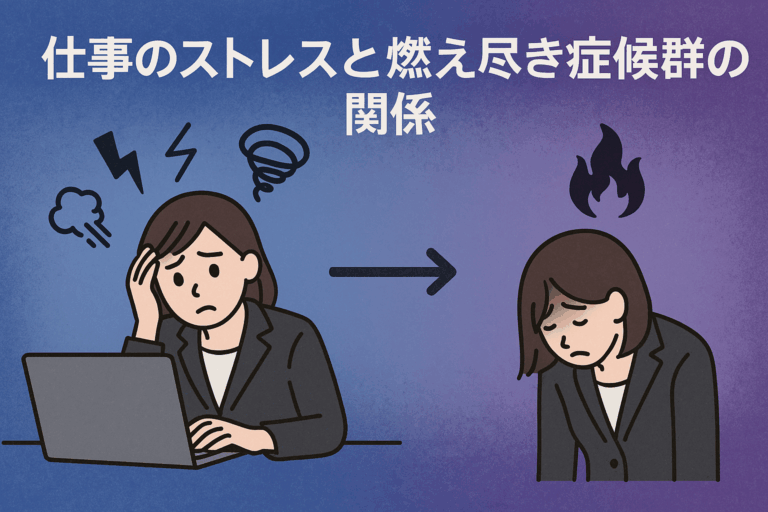
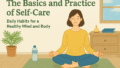


コメント