Work Style Reform and Mental Wellness: How to Build a Sustainable Way of Working
最近、働きやすさ、ワークライフバランスといった言葉をよく耳にするようになりました。でも実際のところ、自分の働き方を見直そうとしても、じゃあ、何からどう変えたらいいのか?と戸惑うことってありませんか?
私自身、数年前まではもっと頑張らなきゃと常に気を張って働いていました。でもある時、気づけば心も体もヘトヘトに。効率を追い求めすぎて、大切なものをすり減らしていたんですよね。
この記事では、働き方改革、心の健康をテーマに、持続可能な働き方と生き方について、私の実体験も交えながら考えてみたいと思います。
なぜ心の健康が今これほど注目されているのか?
近年、職場でのメンタルヘルスの問題──うつ病や燃え尽き症候群(バーンアウト)など──が深刻化しています。私の周りでも、真面目で優しい人ほど心を壊してしまうケースを何度も見てきました。
厚生労働省の調査によると、精神疾患による労災申請は年々増加しており、単なる労働時間の短縮だけでは追いつかない時代に入ってきています。
私自身も、ストレスと燃え尽き症候群のはざまでという状態にいたことがあります。あの頃は、夜中に突然涙が止まらなくなったり、朝ベッドから起き上がれなかったり……。まさに「心のSOS」を無視し続けた結果でした。
このあたりについては、別の記事燃え尽き症候群からの回復:「休む勇気」が心を救う理由でも、詳しく書いています。
リモートワークと自由の裏にある落とし穴
働き方の多様化が進み、在宅勤務やフレックスタイムなど柔軟な働き方が可能になってきました。一見、理想的な変化のように思えますが、その裏でオンとオフの境界が曖昧になった、自分を律するのが難しくなったといった悩みも多く聞きます。
実際、私もリモートワークを始めた当初、仕事とプライベートの切り替えができず、常になんとなく働いてる状態になってしまいました。自由には、自己管理という新たな責任が伴うんですよね。
社会・企業・個人ができること
社会:制度設計は変わり始めている
たとえば北欧のフィンランドでは、週4日勤務や1日6時間労働の試験導入など、労働と幸福度のバランスを重視した取り組みが進んでいます。
日本でも、勤務間インターバル制度やストレスチェック制度が導入され、少しずつではありますが変化の兆しが見え始めています。
企業:マインドフルネスや柔軟な制度の導入
Googleが導入したgPause(マインドフルネスプログラム)や、ヤフーの副業容認制度などは、社員の創造性や心の健康を高める試みとして注目されています。
私が以前勤めていた会社でも、週に一度のおしゃべりタイムが導入されてから、同僚同士の空気が和らぎ、誰かが調子を崩したときも自然とフォローし合える雰囲気ができていきました。
個人:セルフケアの習慣化がカギ
制度が整っても、最終的には自分で自分を整える力が欠かせません。私が意識して取り入れているのは、以下のようなことです:
•朝の5分瞑想
•夜のデジタルデトックス(スマホを20時以降は触らない)
•毎日の小さな散歩
これらを無理なく続けることで、心の揺らぎに気づけるようになり、仕事の質も自然と上がっていきました。セルフケアの基本についてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。
持続可能な働き方に向けて
成果よりも幸せに働けるかが問われる時代へ
これからの時代、問われるのはどれだけ成果を出せるかではなく、どれだけ続けられる働き方か、幸せに働けるかだと思います。
たとえ短期的な成果が出ていても、心がすり減っていたら意味がないですよね。長期的に見れば、心身が整っている人の方が、結局は良い仕事をし続けられるのだと思います。
助けを求められることが大切
私が本当に救われたのは、弱さを見せてもいいと思える仲間や環境でした。限界ですと言える空気があるだけで、人はずっと楽になれるものです。
バーンアウトを防ぐ働き方は、頑張りすぎる前に声を出せる文化を持つことから始まるのだと、今ならよく分かります。
おわりに:働き方改革の本質とは?
働き方改革とは、単に効率化を目指すことではなく、人間らしさを取り戻すプロセスではないでしょうか。
心の健康を軸にした働き方は、個人の幸福だけでなく、組織や社会全体の持続可能性にもつながります。
私たち一人ひとりが、自分にとってのちょうどよい働き方を見つけていくこと。これこそが、これからの時代に必要な改革なのだと思います。

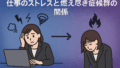
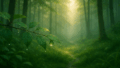

コメント