Defensive Routines: Why We Reject Different Opinions and How to Move Beyond Them
こんにちは。今日は習慣的な防衛について、少し私自身の体験も交えながら書いてみたいと思います。
無意識に、心が閉じてしまうとき
誰かに自分の意見を否定されたとき、「いや、でもさ…」と反射的に反論してしまったこと、ありませんか?
私はあります。たくさん。
こうした反応の背後にあるのが、習慣的な防衛(defensive routines)という心の働きです。
これは、他人からの批判や異なる意見を受け取るとき、自分の価値や考え方が揺らぐのを無意識に避けようとする心理的なクセ。思考のシャッターが、自分でも気づかないうちにガシャッと閉まってしまうような感じです。
本当は学びや成長のチャンスなのに、私たちはそれを危険と感じて遠ざけてしまう。とても人間らしい反応ですよね。
防衛反応の正体は、守りたい気持ち
私たちが異なる意見に防衛的になるのは、たとえばこんな背景があるからだと言われています:
•自分が正しいと思いたい気持ち
•批判を人格否定と感じてしまう思考のクセ
•過去の失敗や恥ずかしさを思い出す恐れ
•自分という存在が崩れてしまうような不安
こうした感情は、誰にでもあるもの。だからこそ、防衛的になるのも自然なことなんです。
私の実体験:指摘された瞬間、心がざわついた
数年前、仕事のプロジェクト中に、同僚が私のコードを見てこう言いました。
「このポインタの使い方、ちょっと危ないかも。メモリリーク起きるかもしれませんよ。」
その瞬間、私はカッとなってしまって、そんなことあるかよ!と、つい語気を強めてしまいました。今思えば、相手は冷静にアドバイスしてくれただけなのに、私は自分の能力を否定されたように感じてしまったんですね。
後から見直したら、彼の指摘は正しかったし、感謝すべきことでした。でも、そのときは自分を守る反応が勝ってしまったんです。
こういうときにこそ、手放すことを学ぶという姿勢が必要だと今では感じています。
防衛がもたらすもったいなさ
このような防衛反応を無自覚に続けていると、実はこんな弊害が生まれてしまいます。
•成長のチャンスを逃してしまう
•新しい価値観を受け入れられなくなる
•人間関係に壁ができる
つまり、自分を守るつもりが、気づけば自分を閉じ込めてしまうことになるのです。
防衛反応を和らげる、4つのアプローチ
防衛的な態度を少しずつ手放すには、次の4つのアプローチが役立ちます。
1.自分の反応に気づく
いま、私は防衛的になっていないか?と、ふと立ち止まってみること。
身体の反応(心拍数が上がる、肩がこわばる)などからも、気づきが得られます。
2.思考のクセをゆるめる
•間違ってもいい、自分はまだ学びの途中なんだと許す。
•批判は人ではなく意見に向けられていると理解する。
•相手の視点に立って考えてみる。
これはまさに、心の柔軟さを育てることにもつながっていきます。
3.開かれた対話を心がける
•すぐに反論せず、まず深呼吸。
•質問で返す:どうしてそう思ったの?
•違う意見にもなるほどと一言添えるだけで、空気が変わります。
4.哲学的な視点をもつ
東洋思想の中には、防衛を超えるヒントがたくさんあります。
•知足常楽:すべてを正そうとしない心。
•放下(ほうげ):他人の評価を完全にコントロールできないと受け入れる。
•以柔克剛:柔らかさこそが強さになるという考え方。
実際にストア哲学にも通じる、深い知恵だと思います。
対話のなかに、優しさを
もし誰かと意見が違ったとき、こんなふうに聞いてみませんか?
•その考え方、興味深いですね。どうしてそう思ったんですか?
•他の視点から見ると、どうなるでしょう?
•その話、私にとって新鮮でした。ありがとうございます。
大切なのは、勝ち負けではなく、つながること。
最後に:守ることより、育てることへ
防衛反応は、私たちが何かを大切に思っている証です。
だから、それ自体を否定する必要はありません。
ただ、「いま私は守っている?それとも、わかろうとしている?」
そう自分にそっと問いかけてみるだけで、心の扉が少しだけ開くかもしれません。
防衛を手放すことは、負けではなく、自由への一歩。
もっと素直に、もっと柔らかく、人とつながれる自分になっていけたらいいですね。

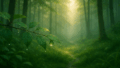
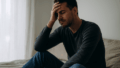

コメント