Recovering from Burnout: How the Courage to Rest Can Save Your Mind
──燃え尽き症候群を越えて:休むことは逃げじゃない、自分を取り戻す勇気だ
頑張り続けた先に、待っていたもの
もっと頑張らなきゃ、止まったら置いていかれる…
そんな思いで、私は長いこと働き続けてきました。
朝は早くから出社し、夜遅くに帰宅。
休日も学ばなきゃと自己啓発書を読みあさり、パソコンの前に座る毎日。
誰よりも努力すれば、きっと報われると信じていました。
けれど、そんな日々の中で、心のどこかが少しずつすり減っていたのです。
燃え尽きるなんて、自分には関係ないと思っていた。
でもある朝、布団から起き上がれなくなりました。
突然のブレーキ——燃え尽き症候群の現実
その朝、体は鉛のように重く、頭も働かない。
スマホを持つ手も、自分のものじゃないように感じました。
ただただ天井を見つめて、気づけば涙が流れていた。
理由もなく、止まらない涙。
心療内科を受診した結果は燃え尽き症候群(バーンアウト)。
医師から「真面目で責任感が強い人ほどなりやすい」と言われ、
そうなのかもしれないと、どこかで納得している自分がいました。
休む勇気との出会い
「しっかり休まないと、本当に戻れなくなりますよ」
そう医師に言われても、私はなかなか受け入れられませんでした。
休むこと=怠けること。
そんな思い込みが、強く根を張っていたからです。
けれど、心も体も限界でした。
何もしない時間が怖くて、最初の一週間は苦しかった。
罪悪感ばかりが膨らみ、みんなは働いてるのにと自分を責め続けていました。
でもある日、ふと公園を歩いていたとき、小さな花が風に揺れているのを見て、
なぜか涙が出ました。
自分はこんなものすら、見えなくなっていたんだ
それが、心の回復の始まりだったように思います。
セルフケアという小さな習慣
その日から、私は少しずつ生活を整えていきました。
朝はゆっくりお茶を飲みながら読書をし、無理のない範囲で散歩をする。
今日できたことを小さなノートに書きとめて、
できなかったことよりできたことに目を向けるようにしました。
完璧を目指さない。
【▶参考記事:完璧主義を手放すと、生きるのが楽になる理由】
カウンセリングにも通い、自分がいかに他人の目や成果に縛られていたかに気づけました。
そしてようやく、自分にこう言えたのです。
頑張らなくても、あなたは大丈夫だよ。
メンタルヘルスを大切にする生き方
数か月の休養を経て、私は職場に復帰しました。
以前よりも心に余裕があり、他人と比べなくていい、自分のペースでいいと思えるようになりました。
それが自然とまわりにも伝わったのか、職場の空気も少しずつ柔らかくなっていきました。
自分を犠牲にしない働き方。
【▶関連記事:「働き方改革」と「心の健康」──心がすり減らない働き方を考える 】
休むことは決して逃げではなく、自分を守るための選択です。
まとめ:本当の勇気とは、立ち止まること
私たちの社会では頑張ることが美徳とされています。
だからこそ、休むことには罪悪感を抱いてしまいがちです。
でも、本当に勇気がいるのは走り続けることではなく、
立ち止まることだと、私は燃え尽きた経験から知りました。
もう頑張れないと思ったとき、
どうかその声を無視しないでください。
休むことこそが、再び自分を育て直すための、大切な時間なのです。
【▶あわせて読みたい:心がざわつくとき、どう整える?】
あなたの心は、ちゃんと休めていますか?

もし今、少しでもしんどいと感じていたら——
まずは深呼吸をして、自分を責めるのをやめてみてください。
休むことに、もっと優しくなってもいいのです。


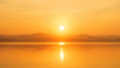

コメント