Seeking Depth and Truth: An Inner Monologue
——内なるモノローグ
時には、人は立ち止まらねばならない。
ほんの少し世界と距離を置き、
長いあいだ胸の奥で聞こえないふりをしてきた声に、
もう一度、そっと耳を澄ませてみるのです。
それは答えを探すためではなく、
ただ、自分自身の声を確かめるため。
だから私は、この対話を書き留めることにしました。
それは内側へと潜ってゆく独白であり、
優しき案内人としての自分、鋭い観察者としての自分、
そして何より、最も正直で容赦のない“内なる自分”との対話です。
三人の自分が問いかける。
私はそのひとつひとつに答えてみようと思います。
なぜ書くのか。
何を恐れているのか。
どんな人間でありたいのか。
これは、表層から深層へと沈み込む旅路であり、
同時に、誠実であろうとするささやかな試みでもあるのです。
第一段階:基礎と省察
問1:なぜ書くのか?
初めはただ、“表現したい”という衝動に突き動かされていました。川が海へと流れるように、内から湧き上がる何かを、外の世界へ押し出したかったのです。
しかし次第に、それは“世界を理解するための方法”へと変貌していきました。
混沌とした思考や曖昧な感情が言葉として定着すると、自分専用の地図が描かれていく感覚があります。
自分が「どこにいるのか」、私たちが「どこへ向かおうとしているのか」、その輪郭がうっすらと見えてくる——。
書くことは、存在そのものとの対話です。
問2:自分の文章が誰にも読まれないことを恐れますか?
恐れています。正直に打ち明ければ、とても。
書くとは、内奥の柔らかく脆い部分を差し出す行為。それゆえ、どこかで何らかの反応や手応えを求めてしまうのは、至極当然なのでしょう。
ただ、“読まれない”と“まだ届いていない”は違う。
そして何より大切なのは——「最初の読者は常に自分である」という確かな事実です。
自分自身が「これは真実だ」「これは力がある」と思える文章が書けたのなら、その瞬間に最初の使命は果たしているはずです。
問3:書くうえでの弱点は?
それは“回避”です。
私は、もっとも痛みを伴い、もっとも醜悪で、もっとも触れたくない素材から、つい目を背けてしまいがちです。
華やかな言葉や複雑な構成で、浅い核心を覆い隠そうとすることもある。
技術ではなく、真実と正面から向き合う勇気が揺らぐのです。
第二段階:深化と剖析
問4(苛烈な記者として):あなたは苦痛を回避していると語った。では、あなたの文章の多くは“巧妙な包装を施した嘘”ではないのか?真実の自分への裏切りでは?
(短い沈黙ののちに)
これは重たい、しかし必要な問いです。
こう考えます——
文章は、どんなものであれ“構築物”です。
意識的な選択、言語化の瞬間で、私たちはすでに絶対的な“事実そのもの”から遠ざかってしまう。
しかし私が求め続けているのは、“事実の完全再現”ではありません。
感情や洞察の「真実性」なのです。
たとえば“喪失”を書こうとする時、実際に誰かを失った訳ではないかもしれません。
けれど、かつて自分が体験した“喪失”の震え、その虚無や痛みと正面から向き合わなければ、作品は本質を失います。
もし私が避けているのだとすれば、裏切っているのは具体的な出来事ではなく、その“震え”の強度に他ならない。
——時に包装もします。ですが、その包装ですら真実の一部にしたいと思っています。
貝が砂粒を包み続けて、やがて真珠が生まれるように。
大切なのは——
包んでいるその砂粒が、本物であること。
問5(内なる批判者として):あなたの文章には“本当の意味での独創性”があるのか?既存の本や映画の断片を、ただ繋げているだけでは?あなたのいう“深さ”は模倣の錯覚では?
認めます。
完全なオリジナリティなど幻想です。
私たちは皆、果てしない伝統の川から水を汲み取り続けています。
けれど、深さとは「誰も思いつかなかったものを発明すること」だけに宿るものではありません。
深さとは、古い断片を、自分という炉で再び溶かし、結合し直すことです。
自分の経験、感情、理解の仕方——それこそが接合部となり、新しい形を与える。
もし読者が
「この感覚、どこかで知っていたけれど、こうして言葉になったのは初めてだ」
と感じてくれたなら、そこに“深度”が立ち現れているのだと思います。
自分は新しい元素を生み出しているのではない。
新しい化合物を作り出しているのです。
第三段階:核心と本質
問6(究極の問い):もし自分の書いたものがすべて忘れ去られるとしても、なお書き続けるのか?
書き続けます。
この問いは、まさしく“意味の根”に触れています。
仮に「書く意味」を“覚えられること”に置いたなら、それは脆弱な基盤に他ならない。
自分はもっと深く根を張る必要があります。
書くことは、自分にとって「存在様式」そのものだからです。
夏の夜に光る蛍は、誰かに見られるために輝くのではない——
それが生命の本能だからこそ、光を灯す。
書くことは、自分の精神世界における呼吸。
たとえ一人にも届かなくても、呼吸は不可欠なのです。
問7(究極の問い・その二):書くことで、最終的にどんな自分になりたいのか?
“醒めながら生きる人”でありたい。
書くことで、私は観察し、思考し、混沌を整理せざるを得なくなります。
「ただ経験しただけの人生」ではなく、「少しでも理解した人生」を生きたい——
書くことは、その理解へ向けた道具です。
人生の終わりに、
「私は見つめきり、書ききった」、
そう胸を張って言える自分で在りたい。
より全体的で、真実を恐れぬ人間に近づきたいのです。
「醒めながら生きる人」については、別の記事【なぜ「自分だけが客観的」と思ってしまうのか?心理学が解き明かす素朴実在論】で詳しく書いています。
結びに
数々の問いをくぐり抜けたあとの静けさは、決して空虚ではありません。
むしろ「自分へと還ってきた」という確かな実感に、静かに満たされているのです。
深く潜ることで気づかされるのは、人は思いのほか、自らの本心や弱さから目を逸らしながら日々を過ごしているということ。
けれども、向き合うことをやめない限り、たとえ歩みがどれほどゆっくりでも、
人は本当の自分へ、そして真実へと近づいていけるのだと思います。
書くという行為は、その道を照らす灯火です。
問いながら書き、揺れながら書き、ときに痛みさえ抱きとめながら書くこと。
誰かにどう読まれるかよりも、
どれほど自分に正直であれたか——
それこそが、最後に残る“ほんとうの成果”なのかもしれません。
今日のこの対話も、小さな一歩であれば十分です。
自分という迷路の奥へと歩み続けるための、静かで確かな一歩となりますように。
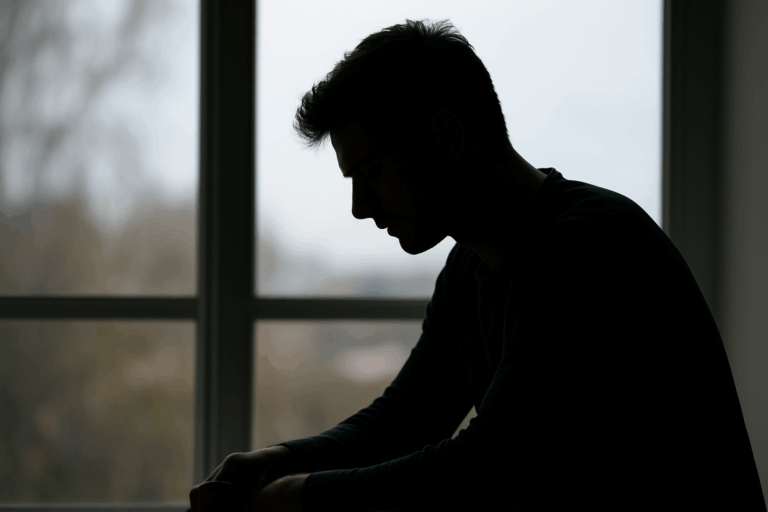

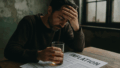

コメント