Blending Light with Dust: Embracing a Quiet Life in Harmony
はじめに:輝きを追い続けた先で、私は疲れていた
和光同塵(わこうどうじん)という言葉を、初めて聞いたのは、心がすっかり燃え尽きていたある日のことでした。
当時の私は、もっと目立たなければ、結果を出さなければと、ずっと肩に力を入れて生きていました。
昇進、資格、プレゼンの成功――SNSに並ぶ知人たちのキラキラした投稿に、自分も負けていられないと、がむしゃらに走っていました。
でも、ある日ふと気づいたのです。
気力も、感情も、まるで絞りカスのようになっている自分に。
そんな私を変えてくれたのが、和光同塵という考え方でした。
燃え尽きた私が出会った、ひとつの言葉
3年前、私は大きなプロジェクトを任され、毎日深夜まで働いていました。
リーダーとして人前に立ち、周囲の期待に応えようと必死でした。
しかし、結果は思うように出ず、関係性も徐々にぎくしゃく。
ある日、上層部から提案をあっさり却下されたとき、何も言えなくなりました。
鏡に映った自分は、目がうつろで、ただの抜け殻のよう。
そんなとき、年配の上司がふとこう言ったのです。
“水が澄みすぎると魚が住まない。人も光りすぎると、折れるんだよ。”
心に、何かがストンと落ちました。
そのとき初めて、和光同塵(わこうどうじん)という思想に出会ったのです。
和光同塵とは?意味と語源をやさしく解説
和光――光を内に秘める、生きるための知恵
和光とは、自分の輝きを抑え、周囲と調和すること。
決して自分を殺すのではなく、内側に光を収めておくことです。
まるで、朝霧の中に広がるやわらかな陽光のように、
強く主張せずとも、人の心を温めるような在り方。
これは、韜光養晦(とうこうようかい)――
力を蓄え、必要なときに静かに放つという東洋の知恵にも通じます。
関連記事:《複雑さをシンプルにする――大道至簡の知恵と実践》の記事もぜひご覧ください。
同塵――俗世の中にいて、染まらない生き方
一方の同塵は、塵=世俗の世界とともに生きること。
ですが、それは流されることではありません。
SNSの評価や他人の視線にとらわれず、
自分の価値観をしっかり持って生きることです。
これは孤立ではなく、自分を見失わないための勇気。
人と関わりながら、なお静かにぶれずに立つ、その強さが込められています。
関連記事:忘れるという知恵──過去を手放す、心の整理術
実体験:控えめな光が、信頼に変わったとき
転職後、私は前に出る役割を手放しました。
代わりに、裏方として若いチームを支える道を選んだのです。
ある会議で、メンバー同士が意見をぶつけ合っていたとき、
私は何も言わずに静かに場を見守りました。
後日、同僚の一人がぽつりとこう言いました。
あなたの沈黙が、一番印象に残った。
声を張り上げずとも、
行動せずとも、誰かの心に届くものがある――
それを実感した瞬間でした。
和光同塵は、目立たないけれど強い
いまの時代、目立つこと、早く成功することが正解のように語られます。
でも、静かに、長く、深く信頼を築く生き方もまた、美しく尊いのだと思います。
和光同塵という言葉は、私にそう教えてくれました。
関連記事:《変わりたいなら、気合ではなく「微習慣」です》のの記事もぜひご覧ください。
まとめ:控えめでも、心を照らす光がある
情報も自己表現もあふれるいまだからこそ、
強く主張せずとも、自然体で心を照らす光が求められているのかもしれません。
和光同塵とは――
•鋭さを隠しても、鈍らず
•光を和らげても、暗まず
•塵に交わっても、染まらず
そんな生き方の中にこそ、
人生を静かに導く本当の強さがあるのではないでしょうか。
最後のひとこと
控えめな光こそ、最も遠くまで届く。
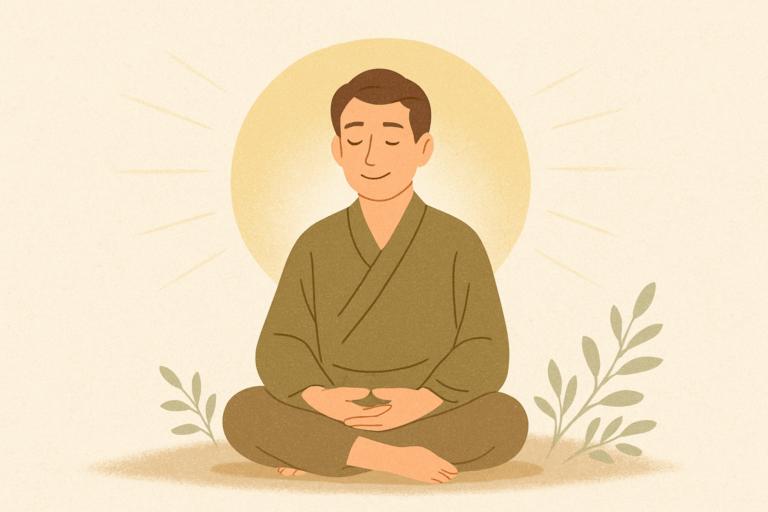



コメント