Letting Go of What We Can’t Control: How Stoic Philosophy Helped Me Find Inner Peace
最近、少しずつストア哲学の本を読み返しています。
きっかけは、数年前の大切な人との別れでした。あまりにも突然で、まるで足元の地面が抜けたような感覚。どうにもならないことに直面すると、人は無力になるものですね。
それまでは、何か問題が起きたときには自分がもっと頑張れば、もっと上手くできたらなんて考えるクセがあって、すぐに自分を責めてしまっていました。
でも、そのときばかりは、どう考えても自分の力じゃどうにもならない現実を前に、ただ茫然と立ち尽くすことしかできませんでした。
「コントロールできること」に集中するということ
そんなとき、偶然手に取ったのが、マルクス・アウレリウスの『自省録』でした。
その中にあった一節が、当時の私には強烈に響きました。
変えられるものに集中し、変えられないものは受け入れよ。
これは、まさに 手放すことを学ぶ──人生の八苦を超える智慧 の核心でもあります。
自分で変えられないことにこだわることが、いかに心をすり減らすか──そのとき私は初めて気づいたのです。
身近な人の死、誰かの気持ち、過去の選択、流れていく時間──どう頑張っても変えられないものに執着して、気づかないうちにたくさんのエネルギーを失っていたのかもしれません。
受け入れるって、そんなに簡単なことじゃない
もちろん、受け入れると言うのは簡単です。でも実際は、本当はまだ受け入れたくないっていう自分が、心のどこかにずっといました。
ストア哲学は、感情を押し殺すことをすすめているわけではありません。
むしろ、感情に流されず、正しく見ることを大切にしていると私は思います。
これは、善意は誤解されるもの?──『与える優しさ』が通じないときにも通じるテーマかもしれません。
泣いたっていい。怒っても、悲しんでもいい。ただ、それをずっと持ち続けるのか、そこから一歩踏み出すのかは、自分の選択なんだ、と気づかされたんです。
日々の内省が、少しずつ私を変えてくれた
それ以来、私は日記を書くことを習慣にしました。
といっても、長々と何かを書くわけではありません。
毎晩寝る前に、ただ一言二言だけでも、
•今日、私は何を受け入れられただろう?
•手放せた感情はあったかな?
•何にイライラして、それはコントロールできることだった?
•どんな小さな進歩があった?
こんなふうに問いかけるだけで、少しずつ心が整っていく気がしています。
心がざわつくとき、どう整える?」という記事でも触れたように、今の自分を見つめる習慣が、自分の変化を静かに支えてくれるのです。
死や無常とどう向き合うか
『自省録』の中で、マルクスはこんなことも言っています。
すでに死んだと思って、残された人生をよく生きよ。
この言葉、私は正直、最初は少し怖かったです。
でも、よく考えてみると、明日が来るとは限らないという前提で生きることって、ものすごく丁寧な生き方だなって思ったんです。
これは 無常の世を生きるということでも深く扱ったテーマです。
明日が当たり前に来ると思ってるから、今日を雑に過ごしてしまう。
でも、もし今日が最後の日だとしたら──誰かにかける言葉、朝の散歩、夕焼けの美しささえも、もっとちゃんと味わえるんじゃないかって。
完璧じゃなくていい。大切なのは、毎日少しずつ進むこと
ストア哲学のいいところは、完璧を求めないところだと私は思います。
格局──どこまで歩いていけるかを決める力 にも書いたように、人生の大きな絵は、日々の小さな選択の積み重ねで描かれていくのです。
失敗してもいい。感情に飲まれても、後悔してもいい。
でも、そこから何か学べたなら、それだけで十分じゃないかと。
最後に:心の平穏は、選び取るもの
私は今でもよく不安になります。
あの人、どう思ってるかな?この判断、正しかったのかな?って、ぐるぐる考える日もあります。
でも、そんなとき、自分に問いかけるんです。
それって、自分でコントロールできること?
もし違うと思えたら、少しだけ手放してみる。
そして、自分にできることにだけ集中する。
それを何度も繰り返していくうちに、少しずつ、心が静かになっていくように感じています。
人生は、いつだって不確かで、不完全で、思い通りにならない。
だからこそ、ストア哲学の今ここを生きる力が、私には必要なのだと思います。
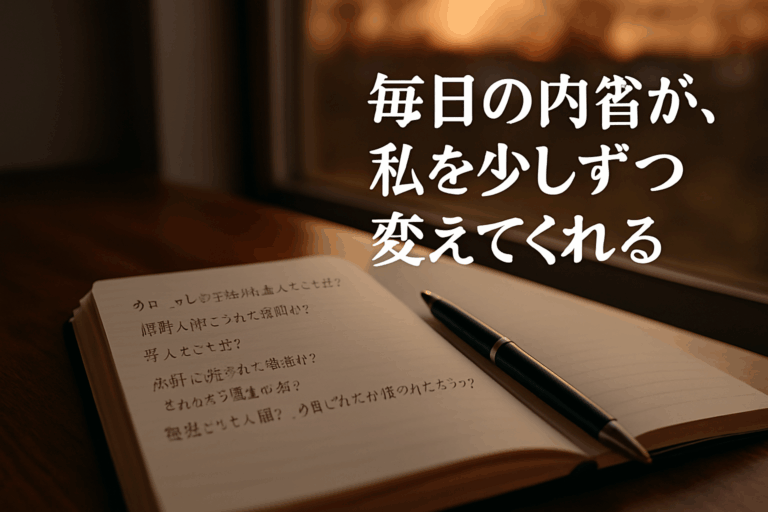



コメント
ストア派哲学の主要な教えについて教えてください。
代表的な人物
– ゼノン(Zeno of Citium):学派の創始者。アテネの「彩色柱廊」(Stoa Poikile)で講義を行い、学派の名前の由来となった。
– セネカ(Seneca):ローマの政治家。怒り、悲しみ、権力への対処について探求し、『人生の短さについて』を著した。
– エピクテトス(Epictetus):奴隷出身の哲学者。内面の自由を強調し、『手引き』に彼の思想のエッセンスが詰め込まれている。
– マルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius):ローマ皇帝。『自省録』に彼のストア哲学の実践が記録されている。
ストア派の発展
1. 初期ストア派(紀元前3世紀)
– 創始者ゼノンの思想を基盤に、クリュシッポス(Chrysippus) らが論理学を発展させました。
– 禁欲主義を強調し、理性による感情の制御を重視しました。
2. 中期ストア派(紀元前2世紀)
– パナイティオス(Panaetius)や ポセイドニオス(Posidonius)によって、より実践的な哲学へと発展。
– ローマ社会に適応し、政治や倫理に関する議論が増えました。
3. 後期ストア派(紀元1世紀~2世紀)
– セネカ(Seneca)、エピクテトス(Epictetus)、マルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius)らが活躍。
– 個人の精神的成長やリーダーシップに焦点を当て、ローマ帝国の支配層にも影響を与えました。