When Kindness Is Misunderstood: Why Giving Doesn’t Always Connect
良かれと思ってやったことが、なぜか裏目に出た、
親切にしたはずなのに、相手がよそよそしくなった……
――そんな経験、一度はありませんか?
私自身も、かつて職場で後輩にかけたアドバイスが誤解を招き、それがきっかけで距離を置かれてしまったことがあります。
あのとき、自分では助けになれたらと思っていたのに、相手には押しつけがましいと感じさせてしまった。そのズレに気づいた瞬間、善意の伝え方について深く考えさせられました。
今回は、私の小さな体験を起点に、なぜ善意がすれ違うのか、どうすれば優しさが届くのかを一緒に見つめていきたいと思います。
うまく届かなかった、あの善意
以前、職場で元気のない後輩に、こういうときは先輩に相談してみるといいよ、私も似たような失敗をして、そのときは…と、経験を交えてアドバイスをしたことがありました。
けれど、その後の彼の態度はどこかぎこちなく、やがて話しかけても反応が薄くなっていきました。
後から共通の同僚に聞いた話では、私の言葉が上から目線に感じられたとのこと。そんなつもりはなかっただけに、ショックでした。でも同時に、善意ってなんだろうと、自分の中で問いが生まれました。
なぜ、善意は誤解されるのか?
1.してあげたいが求めていないにすり替わる
私たちが良かれと思って行動するとき、それが本当に相手にとって必要なことかどうか、つい見落としてしまうことがあります。
たとえば、悩んでいる人がただ話を聞いてほしいだけなのに、こちらが一生懸命アドバイスしてしまう。すると相手は、話す気持ちすら失ってしまうかもしれません。
このようなすれ違いは、失敗から学んだこと――立ち直る力と向き合う勇気 にもあるように、自分の思い込みに気づくことから始まります。
2.相手の今を見逃している
支えたいと思う気持ちが先走って、相手の心の準備やタイミングを無視してしまうこともあります。
元気のない同僚に、「何かあった?」と立て続けに聞くよりも、もし話したくなったら、いつでも聞くよと静かに伝えるほうが、ずっと相手の心に寄り添えます。
善意も、押せば届くものではないんですよね。大切なのは、見守る勇気。
3.支配にすり替わる善意
ときに、相手のためを思ってかけた言葉が、相手の選択や自由を奪ってしまうことがあります。
「やめたほうがいい」「それは無理だよ」という言葉は、相手の未来を決めつけてしまうものかもしれません。
この点は、手放すことを学ぶ――人生の八苦を超える智慧 にあるように、自分の期待を手放すことが信頼の第一歩になります。
善意が伝わるためのヒント
■問いかけから始める
「何かできることあるかな?」「話したくなったら、いつでも聞くよ」――こんな一言が、相手の安心につながります。強要しない優しさは、心の距離を自然に近づけてくれます。
■待つ勇気を持つ
善意は、焦って伝えるものではありません。タイミングが整うまで、じっと待つことも大切です。
忍耐強く待つこと――静けさの中で育まれる力 にあるように、沈黙の中にも深い思いやりは宿るのです。
■伝えるより感じ取る
何か言わなきゃ、助けなきゃ――と思う前に、相手の表情や空気を感じてみましょう。ただ隣にいるだけで伝わる優しさも、きっとあるはずです。
日常の中の伝わる優しさ
•疲れていそうな同僚に「無理しないでね」と声をかける
•コンビニの店員さんに、目を見て「ありがとう」と伝える
•電車で重い荷物を持つ人に「お手伝いしましょうか?」と声をかける
どれも、ちょっとした一歩。でも、こうした小さな行動が、人と人との温かなつながりを育ててくれるのだと思います。
まとめ:優しさは、押しつけないことで届く
善意が通じないとき、私たちは落ち込んだり、距離を置いてしまいたくなったりします。でも、その経験こそが、本当に伝わる優しさを見つけるヒントかもしれません。
•与えることは、奪わないこと
•支えることは、押しつけないこと
•信頼とは、急がずに待つこと
そんな心の姿勢を持てたとき、きっと優しさは、やさしい形で誰かの心に届いていくのだと思います。

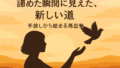


コメント