Why Imperfection Makes Life Truly Complete
欠けた茶碗にこそ、無限の香りが宿る。
なぜ職人は陶器にあえて小さな“ゆがみ”を残すのか。
なぜ桜は満開よりも、七分咲きのほうが人の心をとらえるのか。
禅僧たちは言います。
「完璧になった瞬間、物語は終わる」と。
映画だって同じです。
もし冒頭五分で結末が読めてしまうなら、誰が最後まで心を動かされるでしょう。
人生の面白さは、“未完成であり続けること”のなかにあります。
完璧は、この世界でいちばんやさしい“わな”
経理部が給与を一円の誤差もなく締める——。
それは確かに尊敬される「完璧な仕事」です。
けれど、その「ゼロ誤差」の基準を日常に持ち込むと、
私たちは簡単に落とし穴にはまってしまいます。
・家を買えば人生が満ちると思う
・子どもが名門に合格すれば家族は完璧になると思う
・昇進すれば、もう悔いはないと思う
ところが現実は——
家を買えば内装に悩み、
名門に入れば次は就職が心配になり、
昇進すればさらに上が気になり始める。
“完璧”というゴールラインは、永遠に前へ前へと逃げていくのです。
ギリシャ神話のシーシュポスのように、
どれだけ石を押し上げても山頂で転げ落ちてしまう——。
私たちも同じように、押し上げる行為そのものに意味があることを、
つい忘れてしまうのです。
「満点ママ」が手放した日記
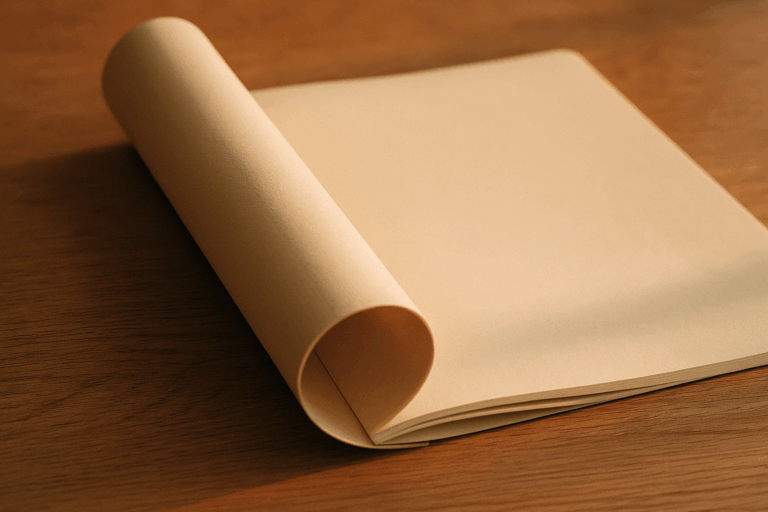
Alisa は職場で信頼される存在であり、同時に“完璧主義”の母でした。
彼女の生活は、いつも張りつめた弓のよう。
・子どもは常にトップでなければ
・家はいつも整っていなければ
・SNS の写真は一枚たりとも失敗できない
「子どもが有名中学に受かり、私が昇進すれば、すべてが完璧になる」——
そう信じていました。
けれど心はいつも疲れ果て、
夫は「一緒にいると息が詰まる」と感じ、
子どもも Alisa の前では笑顔を忘れていました。
“まだ足りないもの”ばかりを数える日々は、
まるで終わりのない借金を払い続けるようでした。
ある日、子どもの絵画コンクールのために、彼女は丁寧に指導を重ねます。
「優勝すること」が、二人の目標でした。
しかし結果は落選。
理由は——「色使いが大胆すぎる」から。
がっかりした Alisa が声をかけようとしたとき、
子どもは友だちに笑顔で見せていました。
「これ、“虹のモンスター”! 先生が“こんな色、見たことない”って!」
その瞬間、Alisa の胸は強く揺れました。
自分が信じていた“正解の形”が、
子どもの純粋な喜びの前では、なんと小さく脆いものだったか。
彼女は“手放す”練習を少しずつ始めました。
・散らかった部屋の“おもちゃ山”を許す
・成績の上がり下がりをそのまま受け止める
・休日はスッピンで出かける
すると、家の空気が変わりました。
夫との会話が増え、子どもの笑い声が戻り、
自分の中に“風”のような時間が流れ込んできたのです。
久しぶりに焼いたお菓子は、よく“腰折れ”しました。
けれど、家族が「ちょっと不格好なバースデーケーキ」を囲んで歌った時間は、
何よりもあたたかく、豊かなものでした。
Alisa は気づきました。
人生は、満点を取る試験ではない。
自分の色で描いていく“写意画”なのだと。
“完璧”ではなく、“よりよく”。
その道のりにこそ、穏やかさと喜びが広がっていたのです。
人生は、ゴールのないマラソン
もし人生をマラソンにたとえるなら、
それは——ゴールテープのないマラソンです。
表彰台も、メダルも、タイマーもない。
それを絶望と呼ぶ人もいるかもしれません。
けれど、むしろその逆。
だからこそ、人生はやさしい。
・ゴールがないから、一歩一歩が目的地になる。
・終わりがないから、どんな瞬間も“始まり”にできる。
子どもの靴ひもを結び直しても、遅れてなんかいない。
夜更けに親のためにお粥を作っているあなたも、
誰よりもまっすぐに走っている。
小津安二郎は言いました。
「人生も映画も、最後に残る“余韻”で決まる」と。
後悔したあの日、迷ったあの選択——
その“完璧ではなかった瞬間”ほど、
時を経るほどに味わい深く、人生を照らすのです。
不完全を抱きしめるための、三つの稽古
「これで十分」を決める
イギリスには、こんな言葉があります。
「完璧は、優秀の敵である」。
レポートも仕事も、“十分できた”と思えたところで切り上げる勇気を。
“欠けた美”を味わう
ゆがんだ陶器、少し音程の外れた歌、
子どもの“似ていない”落書き——。
不完全の中にこそ、生きた質感があります。
“小さな失敗”を祝う
失敗は、ただのデータ収集。
研究者が何度も実験を重ねるように、
今日の“塩辛すぎた料理”も、成功へのひとつの除外条件です。
「欠けた美」については、別の記事【欠けているから、美しい】で詳しく書いています。
おわりに
冒頭の欠けた茶碗を覚えていますか?
茶道では、そのような意図的な欠けを「虫食い」と呼びます。
虫に齧られたような痕があるからこそ、器は息づき、
持ち主とともに時を重ねる“物語”を持つといいます。
私たち一人ひとりも、あの茶碗と同じです。
ひびがあるから光が入り、
満たしきらないから、新しい香りを迎えられる。
人生に“満点の答案”はありません。
けれど、間違えたと思った一歩一歩が、
あなたを“ほんとうの自分”へと近づけてくれるのです。
どうか、不完全な自分を、そのまま愛してください。
そして、永遠の“未完成”の上で、
人生というお茶のいちばん深い味わいを——ゆっくりと楽しんでください。




コメント